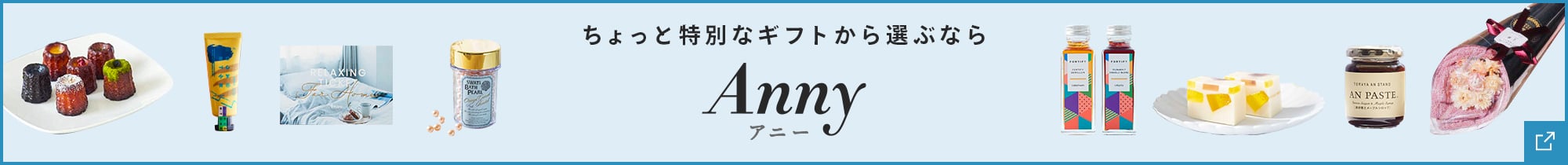- シーンから探す
-
贈る相手から探す
- 彼氏
- 彼女
- 男友達
- 女友達
- 夫・旦那
- 妻・奥さん
- お父さん・父
- お母さん・母
- 両親
- おじいちゃん・祖父
- おばあちゃん・祖母
- 女性
- 男性・メンズ
- 妊婦
- 同僚
- 同僚(男)
- 同僚(女)
- 上司(男)
- 上司(女)
- 部下
- ビジネスパートナー・取引先
- 夫婦
- カップル
- 親友
- 女の子
- 子供
- 男の子
- 赤ちゃん・ベビー
- 乳幼児
- 1歳の誕生日プレゼント
- 2歳の誕生日プレゼント
- 3歳の誕生日プレゼント
- 4歳の誕生日プレゼント
- 5歳の誕生日プレゼント
- 6歳の誕生日プレゼント
- 7歳の誕生日プレゼント
- 8歳の誕生日プレゼント
- 9歳の誕生日プレゼント
- 10歳の誕生日プレゼント
- 18歳の誕生日プレゼント
- 19歳の誕生日プレゼント
- 20歳の誕生日プレゼント
- 21歳の誕生日プレゼント
- 22歳の誕生日プレゼント
- 25歳の誕生日プレゼント
- 26歳の誕生日プレゼント
- 30歳の誕生日プレゼント
- 40歳の誕生日プレゼント
- 50歳の誕生日プレゼント
- 60歳の誕生日プレゼント
- 70歳の誕生日プレゼント
- 80歳の誕生日プレゼント
- 88歳の誕生日プレゼント
- 90歳の誕生日プレゼント
-
カテゴリから探す
- 名入れギフト
- 記念品
- 文房具
- 花
- ビューティー
- こだわりグルメ
- ジュース・ドリンク
- お酒
- 絶品スイーツ
- ケーキ
- お菓子
- プリン
- フルーツギフト
- リラックスグッズ
- アロマグッズ
- コスメ
- デパコス
- インテリア
- キッチン・食器
- グラス
- 家電
- ファッション
- アクセサリー
- バッグ・ファッション小物
- ブランド腕時計(メンズ)
- ブランド腕時計(レディース)
- ベビーグッズ
- キッズ・マタニティ
- カタログギフト
- 体験ギフト
- 旅行・チケット
- ダレスグギフト
- ペット・ペットグッズ
- 面白い
- 大人向けのプレゼント
- 贅沢なプレゼント
- その他ギフト
- プレゼント交換
- 絆ギフト券プロジェクト
- リモート接待・5000円以下
- リモート接待・8000円以下
- リモート接待・10000円以下
- リモート接待・10000円以上
- おまとめ注文・法人のお客様
龍清書本(重要文化財指定)の能筆家・素龍・自筆「法華経」安楽行品(あんらくぎょうほん)・茶道・14-4
-
商品説明・詳細
-
送料・お届け
商品情報
写真の印のうち、下が「杉田玄白」の落款、上が仙台藩医「大槻玄沢」の落款。「自筆原本」出品した自筆の「原文(漢文)」は次の通りです。(画像写真番号14―4)《妙法蓮華經。安楽行品(あんらくぎょうほん) 第十四》《畋獵漁》・・・捕諸悪律儀。如是人等或時来者。則為説法無所望。又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞優婆夷。亦不問訊。若於房中。若経行処。若在講堂中。不共住止。或時来者。随宜説法無所求。文殊師利。又菩薩摩訶薩。不応於・・・・《女人》(文責・出品者)出品した自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。《妙法蓮華経 安楽行品(あんらくぎょうほん)第十四》捕する諸(もろもろ)の悪律儀に親近せざれ。かくの如(ごと)き人等或時に来らば、則(すなわ)ち為に法を説(と)いて・望する所なかれ。又声聞(しょうもん)を求むる比丘(ぴく)・比丘(ぴく)尼・優婆塞(うばそく)・優婆夷(うばい)に親近せざれ、亦(また)問訊せざれ。若(もし)くは房中に於(おい)ても、若(もし)くは経行の処、若(もし)くは講堂の中に在っても、共に住止せざれ。或時に来らば宜しきに随(したが)って法を説(と)いて・求する所なかれ。文殊師利、又菩薩(ぼさつ)摩訶薩、・・・・《まさに女人の身に於(おい)て》(訳・出品者)出品した自筆の「原文の現代語訳文」は次の通りです。《素龍清書本(重要文化財指定)の能筆家・素龍・自筆「法華経」》《妙法蓮華経 安楽行品(あんらくぎょうほん)第十四》《狩猟や漁》・・・・をする等の諸(もろもろ)の戒律を破る者に親近してはならぬ。このような人等が、若し訪ねて来て説法を求められ説法しても、対価を求めてはならぬ。また、声聞を求める比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷に親近してはならぬ。また、問訊してはならぬ。部屋の中で、あるいは経行する場で、あるいは講堂の中でそのような者と一緒に居てはならぬ。たとえ前ぶれ無くやって来て随宜に法を説いても、対価を求めてはならぬ。文殊師利よ。また、菩薩摩訶薩は、まさに、・・・・・《女人の身に》現代語訳の出典・「法華経」(岩波文庫)備考・現代語訳の注記現代語訳は、「法華経」(岩波文庫)と「法華経」のサンスクリット語原典を参照しております。ただし、たとえば「弥勒菩薩」をサンスクリット原典は「マイトレーヤ」としているため、漢文訳をそのまま引用し「弥勒菩薩」と訳しております。また、意味がわかりやすいように漢文からの訳よりも数行分広く訳しております。「出品商品に関する疎明資料(自署と落款)」写真右端が巻二十冒頭の写真、右下角印が伊達家(仙台藩)の家紋写真中央が伊達家(仙台藩)家紋の拡大写真(竹に雀)右から3番目(左端)の右下が「素龍」自筆の署名。左の印のうち、上が「杉田玄白」の落款、下が仙台藩医「大槻玄沢」の落款。「額縁裏面の表記」海外展示の際の表記は、フランス語による表記であるため、額縁の裏面に下記の「表示ラベル」を貼付しております。「法華経 安楽行品 第十四」の東京国立博物館・所蔵の画像は次の通りです。自筆 画像の出典・東京国立博物館・巻十四冒頭重厚勤厳な隷書(楷書)の「法華経(妙法蓮華経)」を出品商品説明出品した「法華経(妙法連華経)」自筆切(断簡)は、松尾芭蕉の親友で江戸・自性院無量寺の住職、柏木素龍・自筆「法華経(妙法蓮華経)」の自筆切(断簡)です。自筆の奥付には、素龍自身の自署が見えます。ほかに、「玄白」と「玄澤」の落款も見えます。「玄白」は、杉田玄白であり、「玄澤」は仙台藩医・大槻玄沢です。原本の大きさ タテ27.1センチ ヨコ13.8センチ。額縁の大きさは、タテ32.7センチ ヨコ24.8センチ。額縁は新品です。稀少価値1・自筆の希少価値出品した「法華経」は、仙台藩が「藩政安泰祈願」のために江戸藩邸を通し、能筆家で有名な「自性院無量寺住職の柏木素龍」に依頼し、藩邸は「寄進」によってその対価としたと推定されております。巻二十の冒頭の伊達家(仙台藩)の所蔵を示す家紋が押捺されている。素龍は松尾芭蕉の親友として、「奥の細道」を清書しております。現在、その書は「素龍・清書本」として「重要文化財」に指定されております。素龍・清書本「奥の細道」(国指定重要文化財)の資料及び画像はこちらをクリックすると閲覧することができます。「奥の細道」(素龍・清書本)は、「草書体」ですが、出品した自筆は、重厚勤厳な隷書(楷書)です。「奥の細道」(素龍・清書本)は、一日あれば清書できますが、隷書(楷書)の「法華経」は、完成し江戸藩邸に納めるまでに数ヶ月を費やしたものと考えられます。「添書」から「法華経」の完成は元禄十一年(1698)です。素龍自筆・「法華経」は長い間、江戸藩邸にありましたが、度重なる「江戸の大火」により散逸消滅しました。わが家に伝来するのは散逸を免れた残りの十分の一程度で、長い間、海外において展示されておりました。「江戸の大火」等による散逸・消失を免れた「法華経」の断簡はその後、屏風立てになっている。さらに時代が下り、茶道の道具として活用された。「法華経」自筆の最終所有者は仙台藩医・大槻玄沢です。2・「極付(きわめつけ)」について杉田玄白の落款は、「箔付」と同時に茶道の道具としての「極付(きわめつけ)」の意味も合わせてもっていたと推定されている。「極付(きわめつけ)」は、「極め札」と同じ意味です。古来、鑑定の目的で添付される「極め札(極付)」は、「折り紙」でありましたため、「折り紙付」とも称された。「極め札」を「極付」とも称するのはこうした理由によるものです。逆に偽物が多いため、信頼性がないという意味で「札付き」の言葉が生まれました。仙台藩は、茶道が盛んであり、家臣が用いる茶道具の信頼性を高めるために当代一の「能筆家」でその書が「名筆」と称された素龍の書に後年、杉田玄白の落款を付すのは仙台藩にとって「極付(きわめつけ)」の意味を持っていたと推定されている。3・字体について「重要文化財」である松尾芭蕉「奥の細道」は、素龍の草書体により記されておりますが「速写」であるため一部字体がくずれております。これは、松尾芭蕉が素龍の友人であった気軽さゆえと考えられている。一方、出品した「法華経」は大藩の依頼であったことと「法華経」ゆえ一文字ごとに精密に記されております。4・紙質「法華経」の自筆に用いられた和紙は、楮(こうぞ)の靭皮(じんぴ)の繊維を原料として漉(す)いた檀紙(だんし)に、雲母紙を載せた「料紙」です。「法華経」を書くために特別に作られたものです。HP出品者の家で代々所蔵している柏木素龍・自筆「法華経」の断簡(断片)のうち、海外貸出の終了した自筆を「海外展示状態」の「額縁付」で出品をいたしました。出品作品以外の所蔵品を紹介した「源氏物語の世界」をご覧ください。ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。
残り 1 点 14490.00円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 05月18日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
-
ラッピング
対応決済方法
- クレジットカード
-

- コンビニ前払い決済
-

- 代金引換
- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
-
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)
-